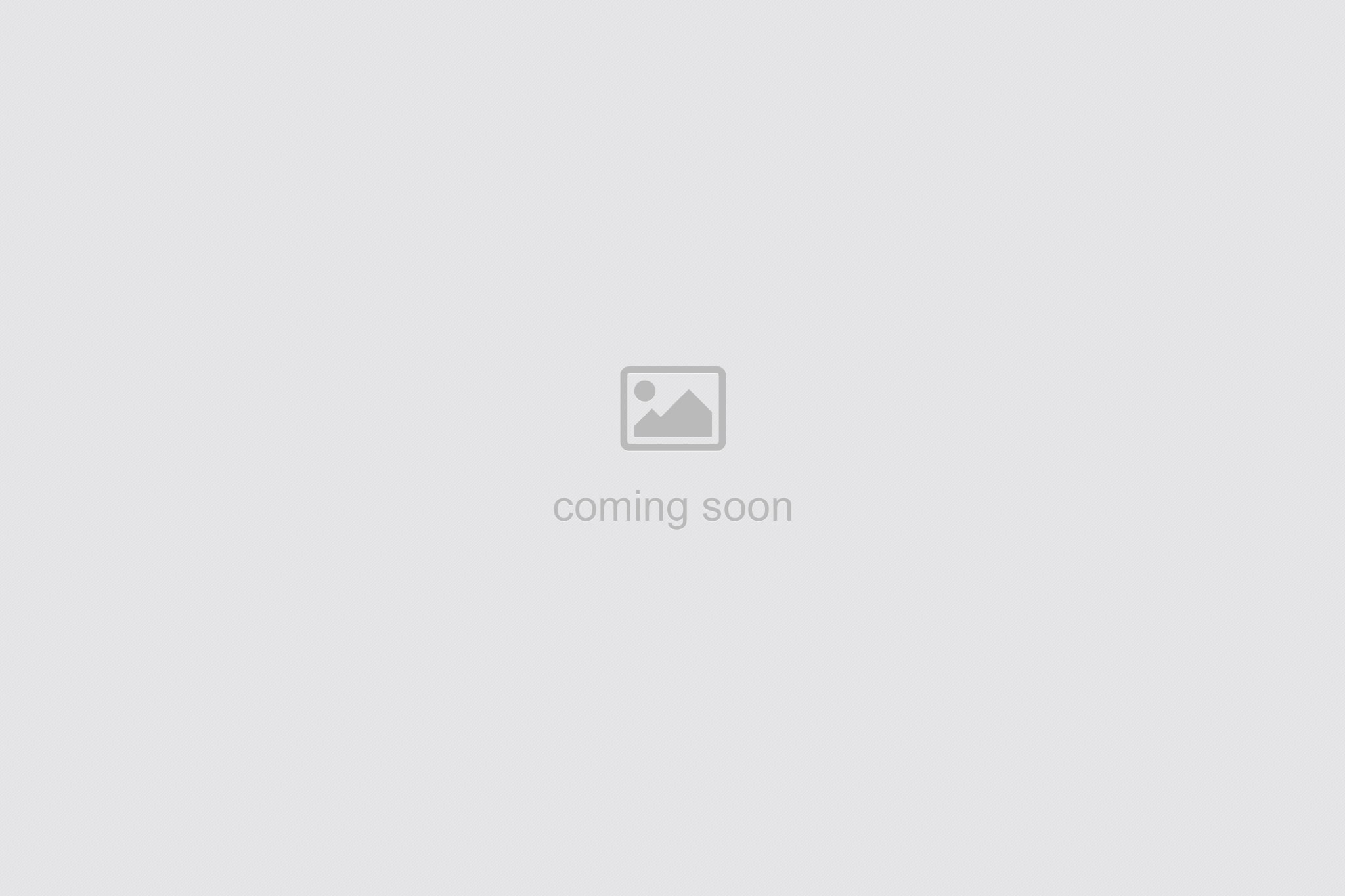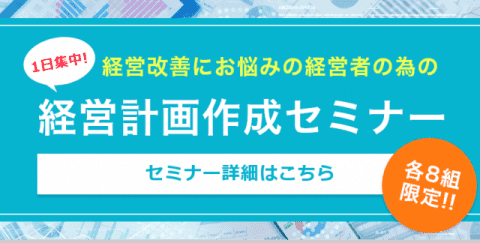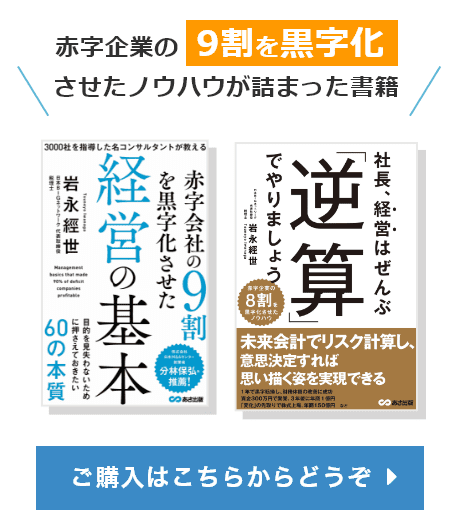2003年05月19日(月)
「第三の開国の時代に」の著者である松本健一氏(麗澤大教授、評論家)は、今秋のNN構想・全国大会で基調講演をして頂くことになっているが、その著書のなかで“日露戦争の正しさ”というテーマで次のような趣旨のことを書いている。
・・・・・氏は、「確信のある所には寛容がある」(天野貞祐)を引用しつつ、政府も国民も日露戦争の“正しさ”を絶対的に信じていたからこそ、内村鑑三ら非戦論に対しても“寛容”であった。
それに対し、大東亜戦争における「不寛容」は、当時の政府と国民の余裕のなさをあらわしており、絶対的な「正しさ」を信じていなかったゆえの、自信のなさであり、それゆえの思想統制や検閲の厳しさがあった・・・・・、と述べている。
私が、この部分を引用したのは二つの戦争の善悪論を問題にしようとしているのではない。「確信のある所には寛容がある」という言葉に触れて、“寛容”ということについて、少し考えてみたいと思ったからである。
高度に情報化された知識社会が進むなか、“ネットワーク化”は時代のキーワードと認識されつつある。“ネットワーク化”とは良好な関係性をいかに構築するかが課題となるが、そのとき“寛容”であることが、その決め手となるのではないだろうか。
“寛容”とは、他人の失敗や欠点をとがめず許したり、自分とは異なるもの(思想や行動など)を理解したりすることであるが、「他人を許したり、理解したり」することを正しく行うことは、意外と難しいものである。
はっきりいえることは、自らの“正しさ”に確信がないところから生じた“寛容”は、妥協や迎合であり、真の寛容とはいえず主体性の欠如を意味する。
では、自らの“正しさ”に確信を持ち得ている人が常に“寛容”であるかというと、そうともいえない。自らの“正しさ”に固執するあまり、“寛容”であることを忘れてしまうことがある。
しかし、思うに「確信ある所には寛容がある」という言葉を信じることができるならば、“寛容”を伴わない自らの“確信”を疑ってみる必要が生じる。その意味において、この言葉の示唆するところは、私にとって価値ある気付きを与えてくれる。
「不寛容」は、余裕のなさのあらわれであり、自分の絶対的な“正しさ”に自信を持ち得ていない証拠である。
“寛容”でありえない対話は、永遠の平行線をつくり、決して重なり合うことができないだろう。
私は、「寛容である」ために自らの“確信”を涵養していきたいと思う。