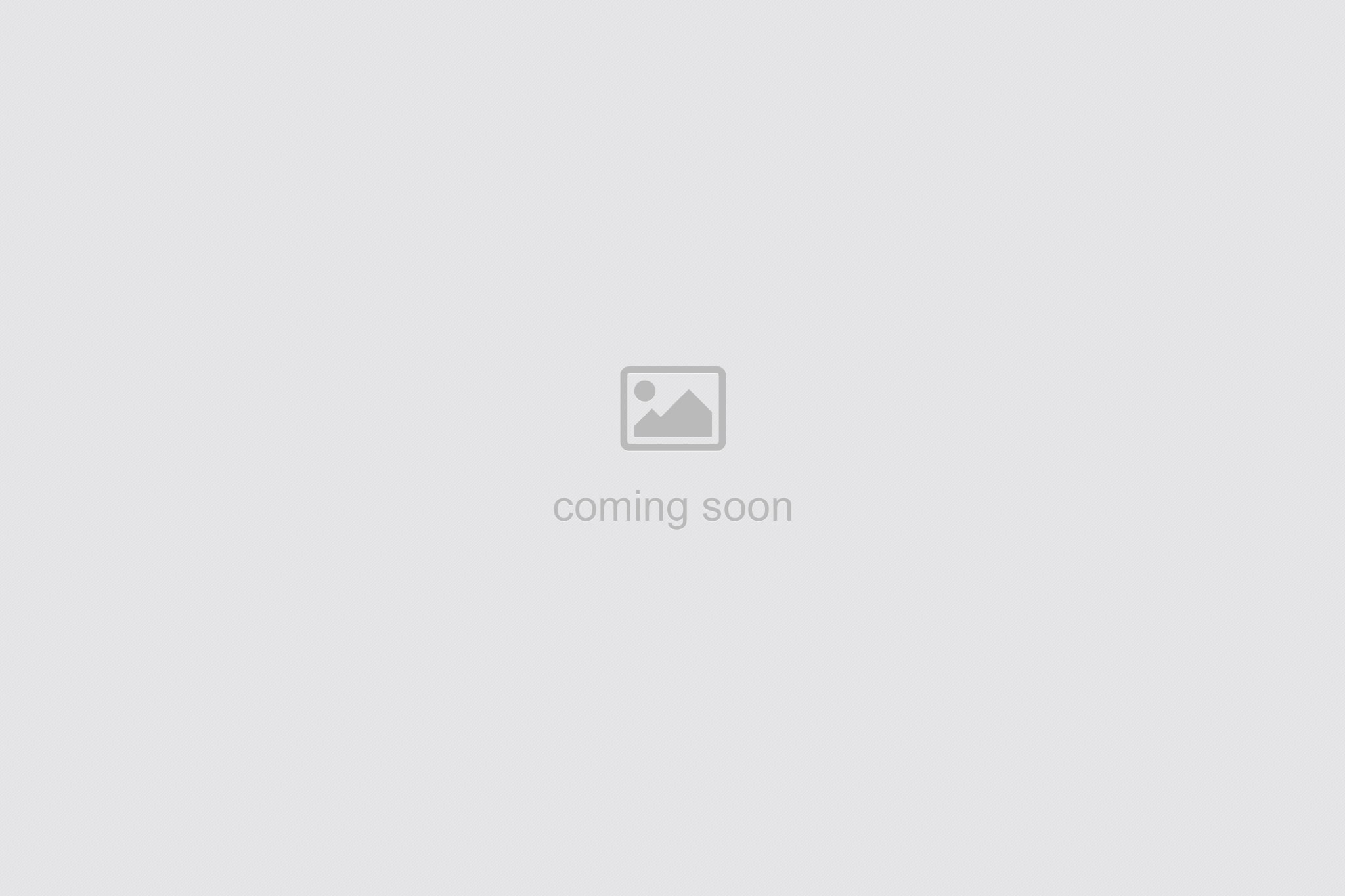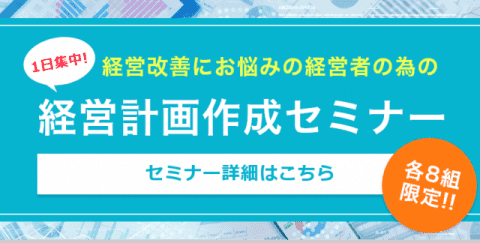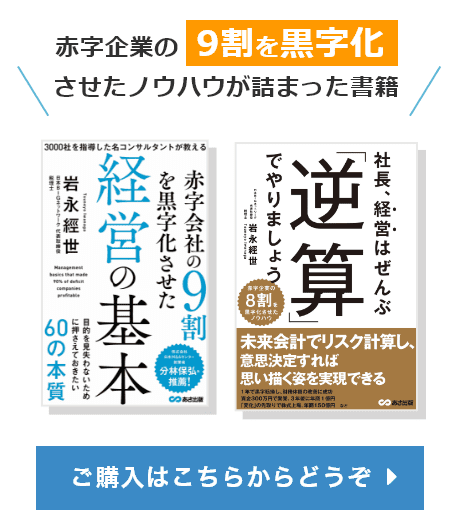2003年12月15日(月)
人間にとって、“馴れる”というのは恐ろしいことではないだろうか。
この言葉には、偽善の響きがあり、現実から逃げようという意識の働きがあるような気がする。
馴れてしまうと、人は変化に疎くなる。抜き差しならない状況が起きているのに、「大変だ!」と感じる力がない。心の片隅で感じているのかも知れないが、行動が伴わないのである。感じる力がないというよりは、むしろ考える力(思考力)がないといったほうが適切であろう。
“馴れる”という行為は、変化を好まず、惰性で生きているようなものだから、今日のように変化が大きい時代において、とても容認できることではない。
業績が低迷している企業からの相談があった。決算書の内容をざっとみても、かなり厳しい状況にあるのは、一目瞭然であった。踏み込んで話を聴くと、同族会社の悪しき典型で、経営者一族の“馴れ合い”の図式があった。一族郎党で役員や役職に名を連ね、経費をつかい、暖簾を食いつぶし続けていたのである。
厄介なことに、一度、馴れてしまうと“馴れない状態”にもっていくのは、そうとうの覚悟がいる。自分の都合が、ガン細胞のごとく増殖をし、切除することができなくなるのである。
嫌な現実には目をそむけ、自分に都合がいいことばかりに目がいくのである。だから、“馴れて”いられるのであろうが、経営不振の行き着く先の責任は、いったい誰が取るのであろうか。
このような経営体質の根本にメスを入れることをアドバイスするが、長く続いた馴れ合いの図式は、そう簡単なものではない。死に物狂いで考えないと、変革の糸口を見い出すことができないのは当たり前である。
しかし、面倒くさくなって、日常業務に逃げ込み、考えることを先送りしてしまう。差し迫る危機に対して、温度差があるのだろうか。今までも、どうにかやってきたという、まさに“馴れ合い”の、変化に緩慢な文化が身についてしまっているのだろうか。
もちろん、“馴れ合い状態”を変えるということは、大変なことである。なぜならば、不安定な緊張状態に陥るからである。しかし、何もしないリスク、つまり、未来を失うという現実から目をそむけるわけにはいかないだろう。
今、組織リーダーあるいは組織の一人ひとりに求められていること、それは過去との“馴れ合い”を絶つ覚悟である。
“馴れる”ということの本質は、怠惰であり、すなわち、無目的ということであろう。